はじめに
16〜18世紀のヨーロッパで国富と国家力を高めるために採用された重商主義は、政策の一貫性というよりもさまざまな施策の集合体であった。西欧の国家は「国家の繁栄=国庫の増加」と考え、経済を統制して貴金属と財貨を集めようとした。この思想の中核にあったのが、貴金属の蓄積を重視する「重金主義(bullionism)」と、交易の出超を国富の源とする「貿易差額主義(balance‑of‑trade doctrine)」である。これら二つの潮流は同じ重商主義の内部で対立し、やがて古典派経済学に統合されていく。本報告では、この対立と統合過程を弁証法的視点で考察する。
重金主義の理念と限界
理念
重金主義は、国の富を金銀などの貴金属の保有量で測る思想である。スペインやイングランドでは、アメリカ大陸などの植民地から流入した金銀が国力の源とみなされ、金銀の国外流出を防ぐために厳格な輸出禁止令が出されたbritannica.com。この立場からは、貿易も国内に金銀を引き込む手段とされ、政府は為替や貴金属の取引を規制して国内の通貨準備を維持しようとしたbritannica.com。
重金主義的政策は金銀流出を防ぐ目的で貴金属の輸出を禁止したが、その結果、企業は輸入代金を支払う手段を得られず、貿易自体が停滞した。また、スペインが植民地から得た金銀で他国の製品を購入し、自国の製造業を育成しなかったために、17世紀後半には「最も豊かな国」から「最も貧しい国」の一つに転落したbritannica.com。この経験は、単に金銀をため込んでも国家の持続的繁栄は得られないことを示した。
批判と内在的矛盾
重金主義が抱える論理的矛盾は多い。何より、通貨量の増加が物価上昇を引き起こして輸出競争力を低下させることを認識していなかった。18世紀のデイヴィッド・ヒュームは「価格–重金フロー・メカニズム」を提示し、貿易黒字国に金銀が流入すると国内物価が上昇し、輸出が減少して貿易収支が自動的に調整されると論じたen.wikipedia.org。この考えは、金銀蓄積が永続的な富につながらないことを示し、重金主義の根本を揺さぶった。
貿易差額主義の台頭
背景
重金主義の行き詰まりを受けて、17世紀後半には貿易差額主義が登場した。イングランド東インド会社の関係者であったトマス・マンは『外国貿易によるイングランドの財宝』(1664年)の中で「イングランドには金銀鉱山がない以上、財宝を得る唯一の手段は外国貿易による出超である」と主張しlibertarianism.org、貴金属輸出禁止を批判した。彼は、輸出が輸入を上回る「差額」、すなわち貿易黒字が継続的に金銀をもたらすとした。つまり、貿易自体が国富を生むという考え方への転換である。libertarianism.orgはこのバランス・オブ・トレード主義を後期重商主義の重要な要素と位置付けている。
方法論
貿易差額主義者は、国家が輸出を奨励し輸入を制限する政策を推進すべきだと考えた。植民地を「原料供給地かつ市場」とし、関税や航海法によって外国船を排除して国内船舶を保護するなどの政策が導入されたeconomicshelp.org。その狙いは、輸出産業を保護・育成し、貿易黒字によって金銀流入を確保することであった。重金主義のように金銀輸出を全面的に禁止するのではなく、貿易を通じて金銀を得るという点で一歩前進している。
限界
しかし、貿易差額主義にも内在的矛盾があった。一国が恒常的に貿易黒字を維持しようとすれば、他国は必然的に赤字を抱える。17世紀のオランダが豊富な金銀蓄積によって繁栄した経験は、必ずしも他国に適用できないことを示した。『国富論』でアダム・スミスは「貿易差額の教義ほど馬鹿げたものはない」と批判しen.wikipedia.org、自由貿易こそが相互利益をもたらすと論じた。また、デイヴィッド・ヒュームの価格–重金フロー・メカニズムは、貿易黒字の持続が不可能であることを指摘したen.wikipedia.org。そのため、貿易差額主義は重金主義の矛盾を克服しきれず、むしろ別の矛盾を生んだと言える。
弁証法的分析
正(テーゼ):重金主義
重金主義は、16〜17世紀に出現した「国の富=金銀蓄積」という単純なテーゼである。スペインの例のように、初期には大量の金銀流入が国家財政を潤し、軍備や宮廷文化を支えた。しかし、金銀の過剰蓄積は国内生産を抑圧し、財政収支の悪化を招くという反作用を内包していたbritannica.com。
反(アンチテーゼ):貿易差額主義
この矛盾に対する反動として生まれたのが貿易差額主義である。トマス・マンらは「鉱山のない国でも貿易黒字によって金銀を獲得できる」として重金輸出規制を批判し、輸出拡大と輸入抑制を主張したlibertarianism.org。しかし、この教義も国際貿易の本質を誤解し、各国が同時に出超を維持することの不可能性や、価格調整メカニズムによる自動的な修正を無視していた。
合(ジンテーゼ):古典派経済学と自由貿易
重金主義と貿易差額主義の対立を統合したのが18世紀後半以降の古典派経済学である。ヒュームは金銀流入が物価上昇と輸出減少を引き起こし、最終的には金銀が流出する「価格–重金フロー・メカニズム」を提示して、貿易差額の維持が不可能であることを理論的に示したen.wikipedia.org。スミスは『国富論』で重商主義を「制限と規制の体系」と批判し、各国が比較優位に基づいて生産と貿易を行えば互いに利益を得られると主張したen.wikipedia.org。これにより、金銀や貿易差額へのこだわりは批判され、富の源泉は生産力と労働分業にあるという新たな認識が広がった。
さらに、同時期に重商主義政策の弊害—特権商人の利権強化、行政の腐敗、植民地の搾取—も明らかになったwifa.uni-leipzig.de。こうした反省と批判の積み重ねが、自由貿易や比較優位を中心とする新しい枠組みへの移行を促し、重商主義は歴史的役割を終えた。
結論
重金主義と貿易差額主義は、ともに国家の富を外部からの貨幣流入に求めた点で共通しているが、その方法論に違いがあり、矛盾を抱えていた。重金主義は貴金属の輸出を禁じて蓄積を図ったが、実際には国内産業の発展を妨げ、スペインの衰退が示すように持続的な富をもたらさなかったbritannica.com。貿易差額主義は貿易黒字を通じて金銀を得ようとしたが、すべての国が同時に出超を達成することは不可能であり、価格–重金フロー・メカニズムが示す通り自動的に調整されるen.wikipedia.org。両者の矛盾は、ヒュームやスミスなどによる自由貿易理論を通じて止揚され、19世紀以降は比較優位と国際分業が富を生むという認識が主流となった。こうして重商主義は弁証法的に克服され、近代経済学への架け橋となったのである。


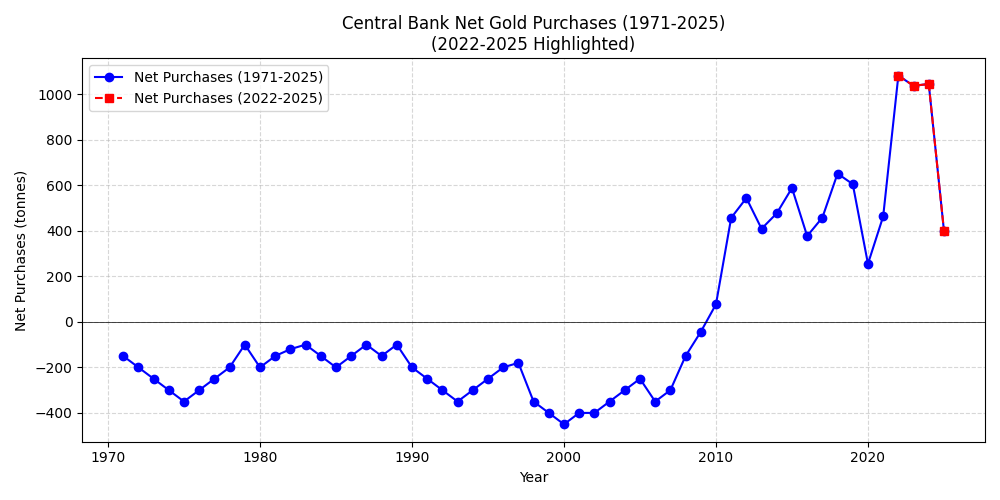
コメント