1. テーゼ(主張):古典的マルクス経済学の理論的枠組み
マルクスは『資本論』で資本主義経済の矛盾を分析し、労働価値説や資本の蓄積・崩壊法則などを展開しました。これらは社会的・歴史的な分析を重視し、社会関係や階級構造に焦点を当てるもので、自然科学的なモデル化や統計的検証よりも理論的・哲学的な考察が中心でした。生産の「総資本」の循環や再生産表式といった図式はある程度の数理を用いましたが、変数やパラメータの定量的調整よりも、論理的な関係性の提示が重視されていました。
2. アンチテーゼ(反論):数理モデルや経験的検証の要求
20世紀以降、経済学全体が数理的分析や計量経済学の手法を取り入れ、政策評価や理論検証に統計データを活用するようになりました。この流れの中で、マルクス経済学が提示する価値や利潤率の傾向、資本の集中・中央集権化などの命題を厳密に検証するためには、数学的モデル化や定量分析が必要だという批判が浮上しました。例えば、利潤率の傾向的低下や蓄積・景気循環を説明するモデルを数理的に構築し、実際の経済データと照合する試みが現れました。また、労働価値説と価格との関係を定式化して検証する“変換問題”への取り組みなども行われました。
3. 総合:現代のマルクス経済学における対話的展開
現代のマルクス経済学者は、古典的理論を維持しつつ、数理モデルや計量分析を取り入れることで理論を発展させようとしています。一方で、過度な数理化が本来の批判的視点や社会関係の歴史的文脈を希薄化させる懸念も論じられます。弁証法的な考え方に基づけば、理論的抽象と経験的検証・数理化は対立するものではなく、相互の緊張関係の中からより豊かな理解が生まれると考えられます。数理モデルは現象のパターンや定量的な関連を明らかにし、経験的検証によって仮説の妥当性や限界が示されます。そして、批判的理論はその背後にある社会構造や権力関係を明るみに出し、モデル化やデータ解析の結果を歴史的・社会的文脈に位置づける役割を果たします。こうした綜合的アプローチにより、マルクス経済学は理論と実証の両面から深化を図っています。


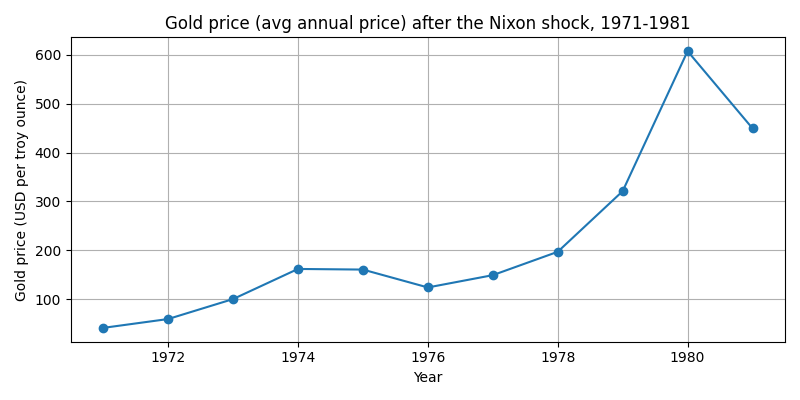
コメント