背景と趣旨
落合陽一氏が提唱する「マタギドライヴ」は、AIが社会の中核を担う時代に、人間がどのように生きるかという問題意識から生まれた概念です。従来の農耕社会や大規模プラットフォームを全面否定せず、その内部や周縁で価値を見出し、地域や文化的な文脈を重視した新しい生き方を模索します。「マタギ」を狩猟採集への回帰としてではなく、農耕と共存しながら自然との対話を繰り返す文化の比喩として用いている点が特徴です。
テーゼ(主張)
- 選択的な生き方の推進: 情報過多の時代に、誰もが大量のデータやAIの結果に流されがちです。マタギドライヴでは、農耕的な大量生産・大量消費のシステムに依存しつつも、自分にとって必要な情報や機会を“狩猟”のように選び取る主体性を重視します。
- ローカルとグローバルの接続: グローバルなシステムとローカルな文化・資源は対立するものではなく、狩猟と農耕の関係のように補完し合うと考えます。計算機による「デジタルネイチャー」を前提にしながらも、地域性や民俗的な価値観を生かすことが求められます。
- アニミズム的倫理観: 本来のマタギ文化には、狩猟行為と宗教的儀式が一体化しているという特徴があります。マタギドライヴでは、技術やAIに対しても畏敬の念を忘れず、自然や他者との共生を志向する倫理観が必要だとされます。
アンチテーゼ(批判と問題点)
- 象徴の恣意的な転用: 現代でもマタギ文化は実在し、宗教観や儀式が生活に根付いています。それを都市部のクリエイティブ層の生き方に重ね合わせると、地域の歴史や生活者の声を消費するだけになりかねません。
- 一部の特権的な層に限定されたモデル: デジタルインフラが整備され、限界費用が低下した先進国でなければ「狩猟的な知的生産」は成立しません。実際には、創造産業に従事する個人事業者やベンチャー経営者など、資本と時間に余裕のある階層しか実践しにくいという指摘があります。
- アニミズムの表層的理解: マタギの儀式性や特有の言葉遣いは、狩猟と日常を切り替えるための「道」として機能してきました。これを単なる「周縁的で自由なメンタリティ」として取り入れると、宗教的背景を喪失したまま行為だけを模倣する危険があります。
ジンセシス(統合)
マタギドライヴには、デジタルネイチャー時代における人間の主体性の回復や、地域文化の再評価という前向きな側面があります。その一方で、象徴の安易な転用や階層格差の問題が指摘されるのも事実です。これらを総合するには、以下のような視点が有効でしょう。
- 比喩の深化と当事者の参加: 「マタギ」という比喩を用いるなら、実際のマタギ文化や狩猟者の声を取り入れ、多元的な視座から概念を練り上げることが不可欠です。
- 包摂的なインフラ整備: 狩猟的な選択と創造が可能となるのは、教育や通信が広く行き渡る社会に限られます。先進国だけでなく多様な地域で実践可能なモデルを目指すべきです。
- 新しい共同体の形成: マタギドライヴ的な生き方は個人主義に傾きがちですが、地域やコミュニティとの協働を重視することで、資本主義の周縁で価値を循環させる「狩猟民的コミュニティ」を構築できます。
要約
マタギドライヴは、AIとデジタル技術が普及する世界で、農耕的な大量生産社会の周縁に身を置きながら、選択的・狩猟的に価値を見出す生き方を提案する概念です。農耕と狩猟、ローカルとグローバル、技術と自然の二項対立を超えようとする点に意義がありますが、実際のマタギ文化の意義を軽視したり、特権的な層に限定されたライフスタイルになりやすいという批判があります。今後は、比喩としてのマタギを深化させ、地域文化や共同体との連携を重視しながら、誰もが実践できる包摂的なモデルへと発展させる必要があります。

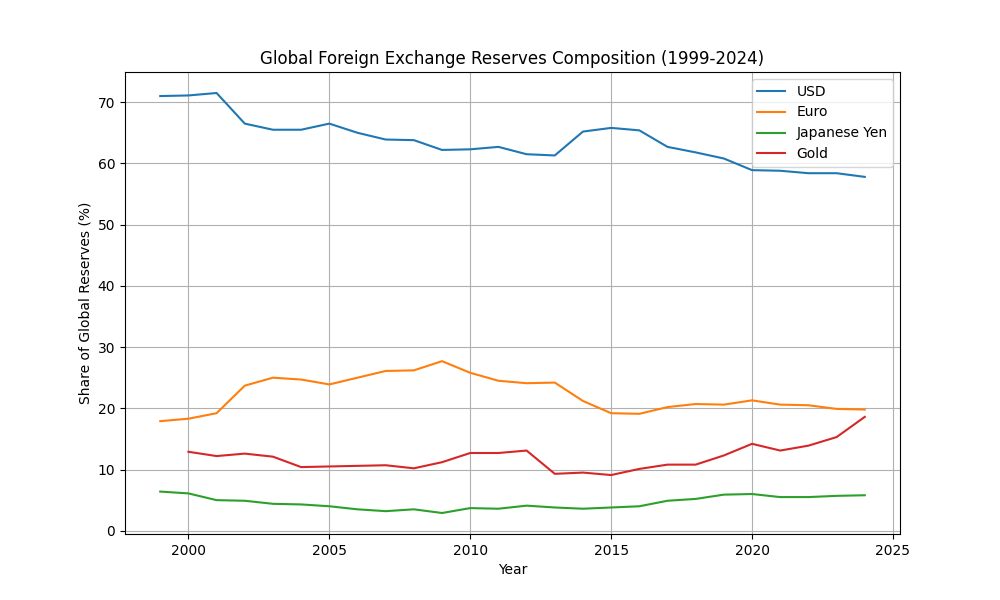

コメント