大気圏とは、地球を取り囲む気体の層を指し、主に窒素(約78%)と酸素(約21%)を主体とする気体で構成されています。この大気は、地球の重力によって保持され、気象現象や生命維持に不可欠な役割を果たします。
大気圏の構造
地球の大気圏は、高度によって異なる特徴を持つ5つの層に分けられます。
1. 対流圏(Troposphere)
- 高度:地表〜約10〜15km
- 特徴:
- 気象現象(雨・雲・風)が発生する領域
- 高度が上がるほど温度が下がる(平均 -6.5°C/km)
- 飛行機の航行が主に行われる
2. 成層圏(Stratosphere)
- 高度:約10〜50km
- 特徴:
- **オゾン層(20〜30km付近)**が存在し、紫外線を吸収
- 高度が上がるほど温度が上昇
- ジェット気流(高速な風)が流れる
3. 中間圏(Mesosphere)
- 高度:約50〜85km
- 特徴:
- 高度が上がるほど温度が下がる(最低 -90°C)
- 流星(隕石)が燃え尽きる領域
- 大気密度が極端に低い
4. 熱圏(Thermosphere)
- 高度:約85〜600km
- 特徴:
- 太陽からの紫外線やX線を吸収し、高温(数千°C)になる
- 国際宇宙ステーション(ISS)が飛行する高度(約400km)
- オーロラが発生する領域
5. 外気圏(Exosphere)
- 高度:約600km〜宇宙空間(約10,000km)
- 特徴:
- 大気圏の最外層で、宇宙空間との境界が曖昧
- 大気分子の密度が極端に低く、ほぼ真空に近い
大気圏の役割
- 生命維持
- 酸素の供給(生物の呼吸)
- 二酸化炭素の循環(植物の光合成)
- 温度調節
- 温室効果ガス(CO₂、H₂O、CH₄)が地球を適温に保つ
- 極端な温度変化を防ぐ(昼夜の温度差が小さい)
- 宇宙線・有害放射線の遮蔽
- オゾン層が紫外線(UV-B、UV-C)を吸収
- 磁気圏が宇宙線(高エネルギー粒子)を防ぐ
- 気象現象の発生
- 雲や雨が形成され、水循環を維持
- 風や気流が地球の熱エネルギーを分配
- 流星の消滅
- 大気との摩擦で小惑星や流星が燃え尽き、地球衝突のリスクを軽減
大気圏と宇宙の境界
- カーマン・ライン(Kármán Line):高度100km
- 国際航空連盟(FAI)が宇宙空間の境界と定義
- ただし、NASAや米空軍では高度80kmを宇宙とみなすこともある
大気圏と航空・宇宙技術
- 航空機
- 旅客機(高度10〜12km):対流圏の上層
- 超音速機(高度20〜30km):成層圏
- スペースプレーン(高度100km以上):熱圏・外気圏へ
- 宇宙開発
- 人工衛星:高度200km以上(熱圏・外気圏)
- 宇宙船の再突入:中間圏・成層圏を通過(摩擦熱による発熱)
人類への影響と課題
- 気候変動(温室効果ガスの増加)
- CO₂増加による地球温暖化
- 異常気象の増加(台風・大雨)
- オゾン層の破壊
- フロンガス(CFCs)によるオゾン層の減少
- 紫外線量の増加による健康被害(皮膚がん・白内障)
- 宇宙ごみ(スペースデブリ)
- 熱圏・外気圏に蓄積する人工衛星の破片
- 衛星運用や宇宙探査のリスク増加
まとめ
大気圏は、生命の維持、温度調節、気象現象、放射線防御など、多くの役割を果たしています。人類の活動による影響も大きく、気候変動・オゾン層破壊・宇宙ごみといった課題への対応が求められています。航空・宇宙技術の発展とも関係が深く、今後の研究や開発が重要な分野となるでしょう。


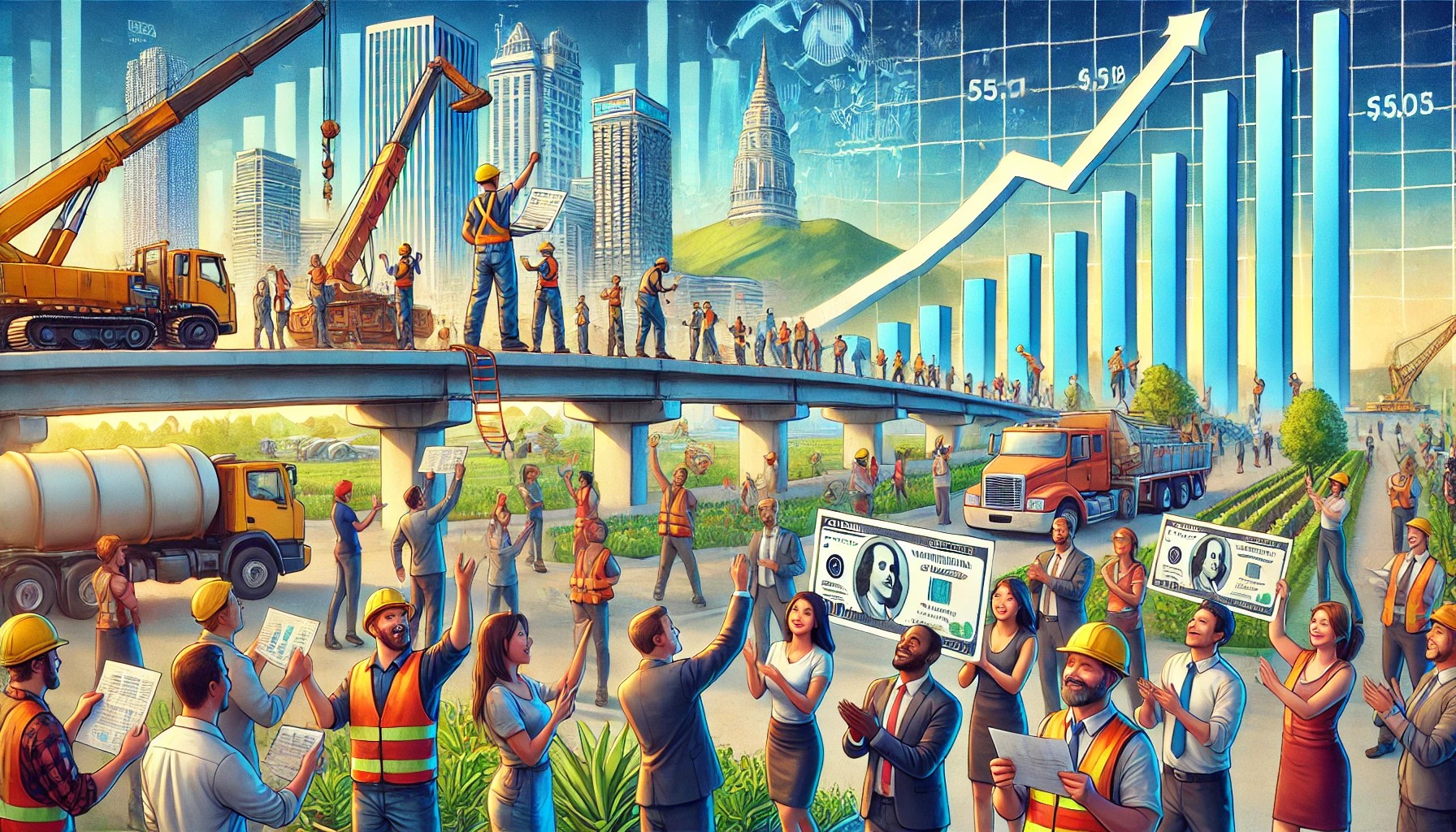
コメント