1. 耐用年数経過後の賃料を計上しない処理は認められるか
国税庁のタックスアンサーによれば、会社が役員に資産を無償または低額で提供した場合、通常受け取るべき対価との差額は経済的利益として役員給与とみなされる。しかし平成24年の国税不服審判所裁決では、役員の家族が会社所有車を専属的に使用した事案につき、車両利用の経済的利益を「取得価額÷法定耐用年数により計算した額」に保険料やローン利息を加えた金額と認定した。この判断から、耐用年数を経過した後には取得原価を基準にした経済的利益の計算は行われないため、減価償却相当額の賃料を徴収しなくてもよいという考え方が示されました。ただし、耐用年数後も中古価値が残る場合に無償貸与すると、その分の経済的利益を給与とみなされるリスクがあるので、市場レンタル料等を参考にした使用料の徴収や車両の譲渡を検討するのが安全です。
2. 耐用年数経過後に利用料を徴収せず維持費だけ会社が負担する合理性を弁証法的に検討
この問題では、「所有権が会社にあるので維持費を負担するのは合理的」とする立場と、「維持費を負担すると経済的利益の供与とみなされる」という立場が対立しました。前者は、自動車検査証の名義が会社である以上、法定点検や登録更新を行う責任は会社にあり、車検切れのリスクを回避する合理性があると主張する。一方後者は、役員へ無償ないし低額で資産を提供すると経済的利益となって課税対象になるため、耐用年数後に維持費を負担し続ければ役員給与と認定される可能性が高いと指摘する。双方を調停する案として、法定点検など所有者として不可避の費用は会社負担とし、日常的なメンテナンスや燃料代は役員負担とする、あるいは維持費相当額を給与として処理するなど、公私の境界を明確にする方法が提案されました。
3. 会社所有の車を100%私用で代表取締役にリースする場合のリース料設定と契約内容
役員への車両貸与では、低額すぎる使用料は経済的利益とされるため、合理的なリース料を設定する必要があります。税務当局が参考とする平成24年裁決では、通常支払うべき使用料は「取得価額÷法定耐用年数+保険料やローン利息の月額」と認定されました。例えば、ある記事では中古車(取得価格300万円、耐用年数2年)の減価償却費と保険・税金等を合計し年額174万円、月額約14.5万円と試算し、私用割合に応じて使用料を算定する具体例を示しています。100%私用であれば、減価償却費や保険料、税金、車検・メンテナンス費用等を全て月割りした金額をリース料とし、燃料費等の変動費は役員が負担するのが妥当です。
リース契約には車両の特定、契約期間(耐用年数内が望ましい)、リース料・支払方法、費用負担区分、使用範囲や禁止事項、事故時の責任分担、返却条件などを明記する必要があります。リース料は毎月一定額を徴収して「定期同額給与」として扱えば、法人税上の損金算入が認められます。耐用年数後に無償貸与する場合は中古車としての価値を考慮し、公私の区分や税務リスクを顧問税理士と検討することが推奨されます。

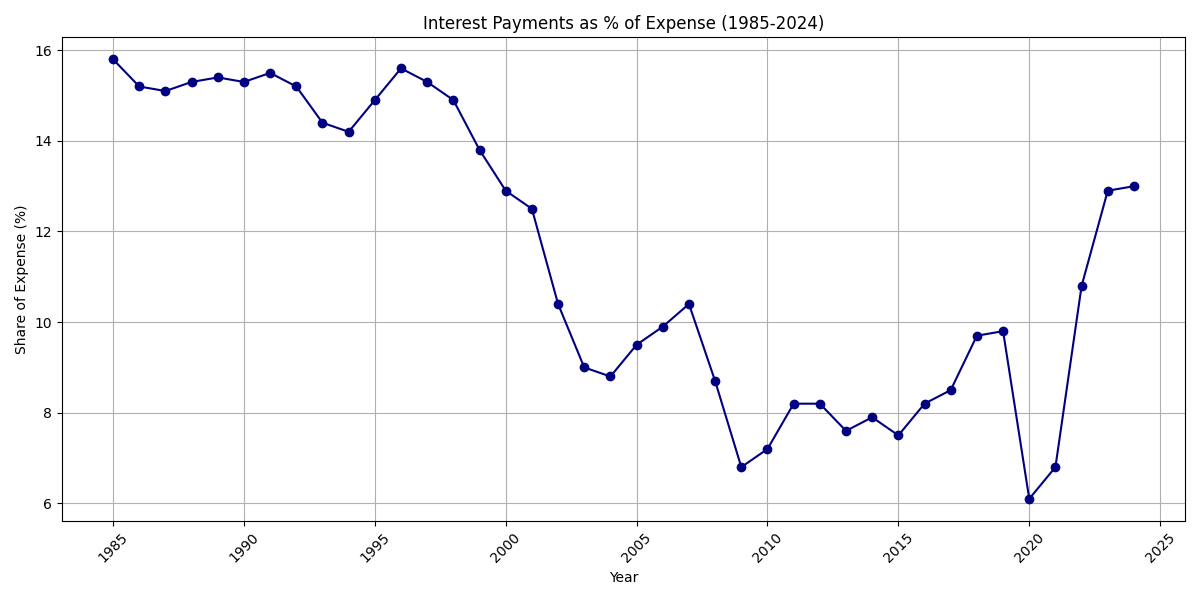

コメント